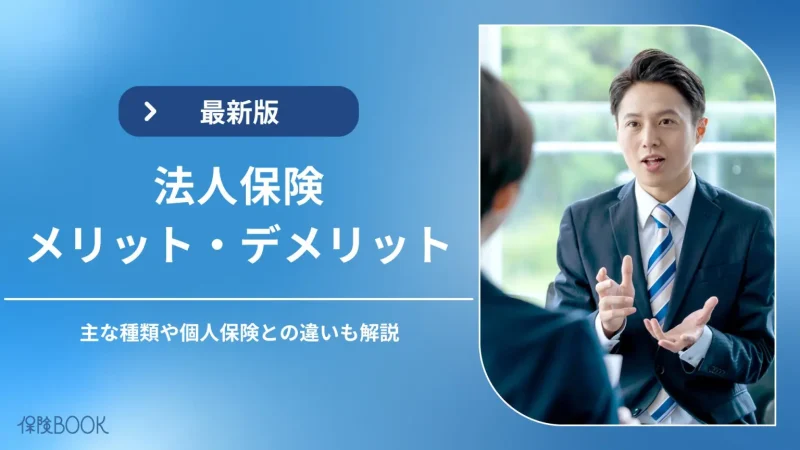
法人保険のメリット・デメリットは?主な種類や個人保険との違いも解説
法人保険は企業経営に伴う様々なリスクに備えられることから、法人保険に加入するべきか悩んでいる経営者の方々もいるでしょう。
ところが、法人保険とはどのような保険なのかを理解せずに加入してしまうと、法人保険のメリットを活かしきれないかもしれません。
そこで本記事では、法人保険のメリット・デメリットや主な種類について解説します。

- 法人保険は企業が契約者となり、経営者・役員・従業員を保障する保険
- メリットは、万が一の備え・事業承継対策・福利厚生の充実
- デメリットは、節税効果が限定的で短期解約で元本割れのリスクがある点
- 自社に合う保険を知りたい方は、無料相談窓口「ほけんの縁結び」の活用がおすすめ。無料で何度でもFPに相談でき、さらにお米がもらえる特典※もあります。

※プレゼント内容は時期により変更となる場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
※本サイトの制作は、不正景品類及び不当表示防止法(景品表示法)を初めとする広告に関連する法規制やガイドラインを遵守して行われております。
※本メディアは株式会社ZNPマーケティングが運営しています。

法人保険とは?
法人保険とは、企業が契約者となり経営者・役員・従業員などを被保険者とする生命保険・損害保険のことです。
保険に加入する目的は多岐にわたり、具体例としては以下が挙げられます。
- 経営者・役員の死亡に対する備え
- 経営者・役員の退職金の原資
- 事業承継のための資金準備
- 従業員に対する福利厚生の一環
法人保険に加入することで、経営していくうえで被る可能性がある多数のリスクに備えることができます。
個人保険との違い
保険商品としての基本的な仕組みは、法人保険と個人向けの保険で違いはありません。しかし、契約する目的や契約者・受取人などの構成、税務上の扱いは異なります。
法人保険と個人向け保険の違いを下表にまとめました。
| 法人保険 | 個人向け保険 | |
|---|---|---|
| 契約者 | 法人 | 個人 |
| 被保険者 | 経営者・役員・従業員など | 本人・家族など |
| 保険料の支払人 | 法人 | 個人 |
| 保険金の受取人 | 原則として法人 (遺族受取の場合もある) | 本人・家族など |
| 税務上の効果 | 課税の繰り延べ (損金算入) | 所得税・住民税の軽減 (生命保険料控除) |
個人向け保険は、個人が抱えうるリスク(医療費・生活費・教育費など)に備えるのに対し、法人保険は企業経営に関わる様々なリスクに備えるのが目的です。
契約形態・加入目的が異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで適切に使い分けることが大切です。
法人保険に加入するメリット
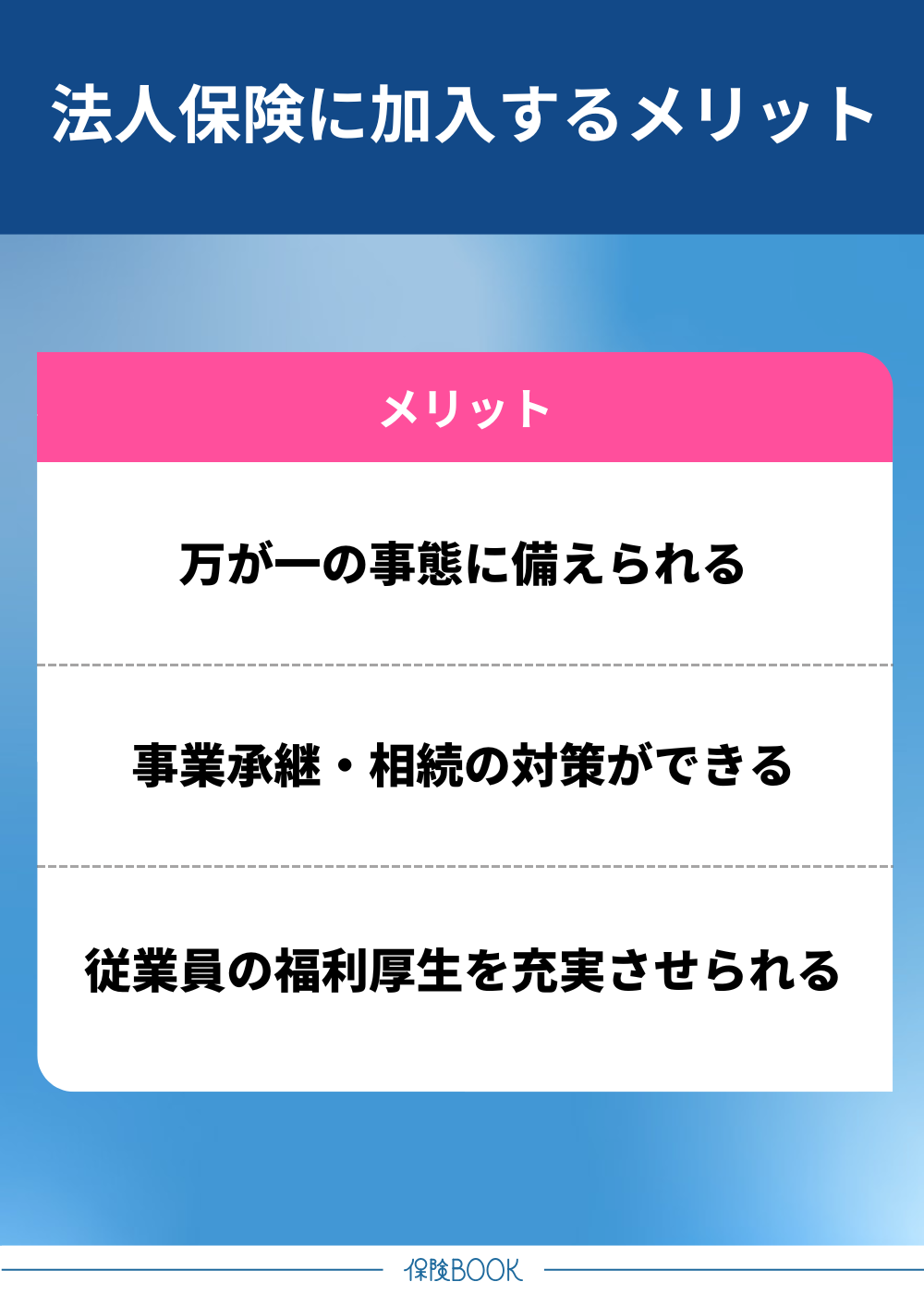
法人保険に加入するメリットは、以下のとおりです。
- 万が一の事態に備えられる
- 事業承継・相続の対策ができる
- 従業員の福利厚生を充実させられる
万が一の事態に備えられる
法人保険に加入することで、以下のような予期せぬトラブルに対応できるのが大きなメリットです。
- 経営者の死亡
- 事故・自然災害などによる損害
- 従業員による横領・不正・情報漏洩
こうした事態が発生すると、会社は突発的に多額の資金を必要とします。経営者が急逝した場合には後継者選定・事業承継の混乱が避けられず、災害による被害では復旧費用や休業による売上減少が直ちに経営を圧迫しかねません。
また、従業員による不正や情報漏洩があれば、顧客からの信頼を失い、取引停止や損害賠償につながる可能性もあるでしょう。
法人保険による備えは返済不要の資金を確保できるため、会社の資金繰りを安定させやすいのが特徴です。

事業承継・相続の対策ができる
法人保険は、将来的な事業承継や相続の場面でも重要な役割を果たします。
その際、契約していた法人保険を解約して得られる解約返戻金を事業承継時の納税資金として活用することができます。
また、経営者が死亡した場合は、死亡保険金を活用して相続税や遺族の生活資金に充てることも可能。遺された家族や会社の経済的負担を抑えられるため、次の経営者へスムーズに移行することができるでしょう。
従業員の福利厚生を充実させられる
従業員が被保険者の法人保険を活用することにより、従業員が安心して働ける環境を整えることが可能です。
具体例としては、以下のような保険が挙げられます。
| 保険の種類 | 概要 |
|---|---|
| 総合福祉団体定期保険 | 従業員の死亡時に遺族に対して死亡保険金を給付 |
| 団体医療保険 | 病気・ケガによる入院・手術などの医療費を保障 |
| 団体長期障害所得補償保険(GLTD) | 長期の就業不能時における収入減少を補償 |
福利厚生が充実している企業は社員定着率や採用力が向上し、企業の成長にもつながります。

法人保険に加入するデメリット
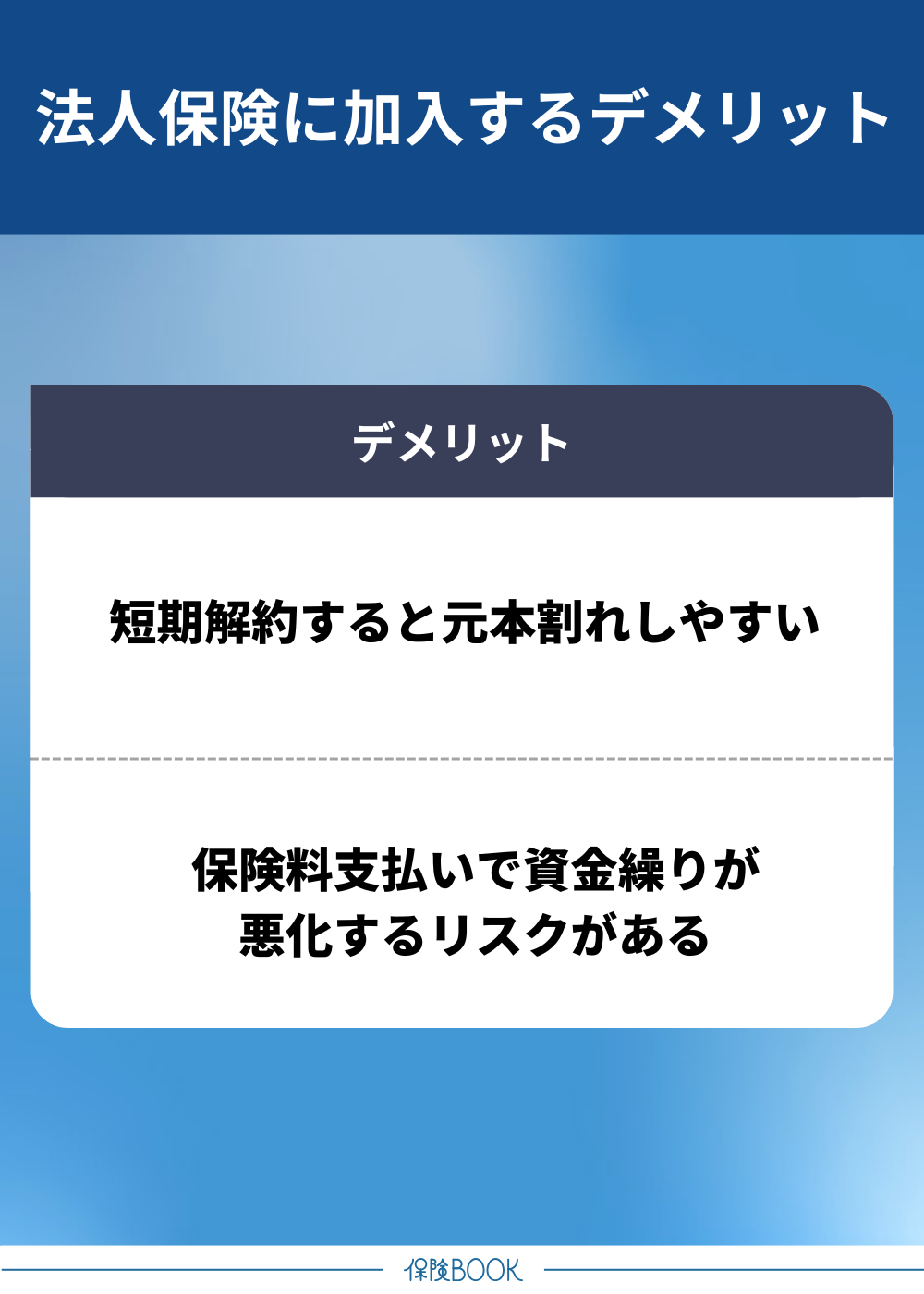 法人保険に加入するデメリットは、以下のとおりです。
法人保険に加入するデメリットは、以下のとおりです。
- 短期解約すると元本割れしやすい
- 保険料支払いで資金繰りが悪化するリスクがある
短期解約すると元本割れしやすい
法人保険は基本的に長期継続を前提とした商品のため、短期解約をすると多くの場合で解約返戻金が払込保険料を下回る「元本割れ」となる可能性が高いです。
経営状況や将来ビジョンと照らし合わせたうえで、計画的に加入することが求められます。
保険料支払いで資金繰りが悪化するリスクがある
定期的に保険料の支払いが発生し、キャッシュフローが悪化する可能性がある点もデメリットです。

特に、保障の手厚い保険ほど保険料が高額になる傾向があるため、保障内容と保険料のバランスを考慮することが大切です。保険料の負担が過剰にならないよう、無理のない契約内容を選ぶ必要があります。
法人保険の主な種類
法人保険は、大きく分けて「生命保険」と「損害保険」の2種類に分類されます。
どちらも企業活動に必要不可欠なリスク対策のため、目的に応じて適切に組み合わせましょう。
法人向け生命保険の種類
法人向けの主な生命保険は、以下の4種類があります。
- 定期保険(長期平準定期保険・逓増定期保険)
- 養老保険
- 医療保険・がん保険
- 収入保障保険
定期保険(長期平準定期保険・逓増定期保険)
定期保険は一定期間の死亡保障がある保険のことで、法人向けには以下の2種類が一般的です。
- 長期平準定期保険
- 逓増定期保険
長期平準定期保険は、長期にわたって経営者・役員の死亡リスクに備える保険です。保険期間中の保障額は一定であり、被保険者が95〜100歳の時に満期を迎える商品が多いのが特徴。定期保険でありながら終身保険のような長期保障を受けられるのがメリットです。

逓増定期保険は、時間の経過とともに保障額が増加するタイプの定期保険です。受け取れる保険金額は基準保険金額(契約時点の保険金)の最大5倍まで増加するため、企業の成長に合わせて必要な保険金を備えることができます。
契約から5〜15年ほどで解約返戻金のピークを迎え、以後は返戻率が減少していくのが一般的。経営者の引退タイミングを解約返戻金のピーク時に合わせて契約するのがおすすめです。
養老保険
養老保険は、保障と貯蓄を兼ね備えた保険のことです。死亡時には死亡保険金を、満期時には満期保険金を受け取れるため、生死に関わらず給付を受けられるのが特徴です。

保険金の受取人は遺族または法人になり、死亡時は遺族受取で満期時は法人受取のように、状況に応じて受取人を分けることもできます。受取人を誰にするかで、税務の取り扱いが変わる点には注意しておきましょう。
医療保険・がん保険
医療保険やがん保険は、経営者や従業員に対する医療保障がある保険のことで、個人向けのものと保障内容に大きな違いはありません。
- 医療保険:幅広い病気・ケガによる入院・手術などを保障
- がん保険:がん治療に特化した保障
経営者・役員を被保険者に設定する事業保障としての活用が一般的ですが、従業員に対する福利厚生として導入することもできます。
法人で団体契約を結ぶことで、従業員が個別契約するよりも保険料が割安になる傾向です。加入者(従業員)自身が保険料を負担する場合でも、福利厚生としてのメリットはあるでしょう。
収入保障保険
収入保障保険は、被保険者が死亡・高度障害状態に陥った際に、遺族が年金形式で保険金を受け取れる保険です。
保険料の負担を抑えつつ、経営者・役員の万が一の事態に備えることができるでしょう。
法人向け損害保険の種類
損害保険は、企業が活動するうえで生じるさまざまなリスクに備える保険です。物的損害・賠償責任・従業員のケガや事故など幅広くカバーされており、以下のような種類があります。
| リスク | 主な保険の種類 |
|---|---|
| 企業の財産に対する損害 | 火災保険・動産総合保険・工事保険など |
| 第三者に対する損害賠償責任 | 自動車保険・PL保険など |
| 事故・災害による損失 | 休業補償保険・興行中止保険など |
| 従業員に対する損害 | 労働災害総合保険など |
なお、これらの主なリスクを1つの保険でまとめて補償する「事業活動包括保険」を取り扱う保険会社もあります。
自然災害の増加や労働環境の変化により、損害保険の重要性は年々高まっている傾向です。

まとめ
本記事では、法人保険と個人向け保険の違いや法人保険のメリット・デメリット、主な種類について解説してきました。
法人保険への加入は、経営者の万が一の事態に対する備えや事業承継・相続対策、従業員に対する福利厚生の充実などのメリットがあります。
法人保険は生命保険・損害保険の2つに大別され、その中でも目的に応じて細かく種類が分かれています。ニーズに沿った法人保険を契約することで、経営上のリスクを軽減させることができるでしょう。

