- 健康・病気について知ってほしいこと
糖尿病対策に運動しよう!体を動かすポイントと注意点を紹介

医療費の自己負担を軽減するため、公的医療保険には高額療養費制度があります。これは、ひと月で一定の額を超えた医療費の自己負担が発生した場合、超過分を支給してもらえる制度です。それでは、いくら以上になったら超過分を負担してもらえるのでしょうか。今回は、高額療養費の自己負担の上限について解説していきます。
目次

高額療養費の上限は、年齢や所得で変わります。年齢に関しては、70歳以上と69歳未満に大きく区分され、70歳以上の方が自己負担額の上限は小さいです。年齢別にいくら以上から適用されるのか見ていきましょう。
70歳以上の場合は、以下の3つに区分されます。
・現役並み所得者
・一般所得者
・住民税非課税等
それぞれの上限額について、詳しく紹介します。
現役並み所得者は、課税所得145万円以上(年収約370万円以上)の人のことです。現役並み所得者の外来・入院の自己負担の上限は、年収によって3段階に分かれます。
・課税所得145万円以上(年収370万円~770万円程度)
80,100+(医療費-267,000)×1%
※多数該当の場合は44,400円
・課税所得380万円以上(年収770万円~1,160万円程度)
167,400+(医療費-558,000)×1%
※多数該当の場合は93,000円
・課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)
252,600+(医療費-842,000)×1%
※多数該当の場合は140,100円
一般所得者は、課税所得145万円未満で住民税非課税等でない人(年収156万円~370円程度)のことです。個人ごとの外来の上限は18,000円/月(年144,000円)、世帯ごとの外来・入院の上限は57,600円/月(多数該当の場合は44,400円)です。
住民税非課税等は、主に被保険者が市区町村税の非課税者の場合です。個人ごとの外来の自己負担上限は8,000円/月、世帯ごとの外来・入院の上限は24,600円/月。被保険者だけでなく、扶養家族すべての人の課税所得がない場合の世帯ごとの上限は15,000円/月です。
69歳以下の人の高額療養費の自己負担の上限は、次の5段階に分けられます。
・住民税非課税者
(月の上限)35,400円
(多数該当)24,600円
・所得210万円以下(年収370万円程度までの住民税非課税者でない人)
(月の上限)57,600円
(多数該当)44,400円
・所得210万円超600万円以下(年収約370万円~770万円)
(月の上限)80,100+(医療費-267,000)×1%
(多数該当)44,400円
・所得600万円超901万円以下(年収約770万円~1,160万円)
(月の上限)167,400+(医療費-558,000)×1%
(多数該当)93,000円
・所得901万円超(年収1,160万円以上)
(月の上限)252,600+(医療費-842,000)×1%
(多数該当)140,100円

高額療養費には、自己負担の上限額を軽減する仕組みがふたつあります。
高額療養費制度では、世帯合算の仕組みがあります。複数の受診や、同じ世帯で同じ医療保険に加入している場合に、それぞれ支払った自己負担額を合算できる仕組みです。
世帯合算を利用することで、ひとりで上限を超えていなくても、世帯で合算して上限を超過した分について払い戻しを受けられます。
上限額の部分でも簡単に触れていますが、高額療養費には多数回該当という仕組みがあります。過去12ヶ月の中で3回以上自己負担の上限に達したとき、4回目以降、多数該当の額まで上限額が下がる仕組みです。
自己負担額が多い医療を複数回受ける場合は、多数回該当を利用できることがあります。
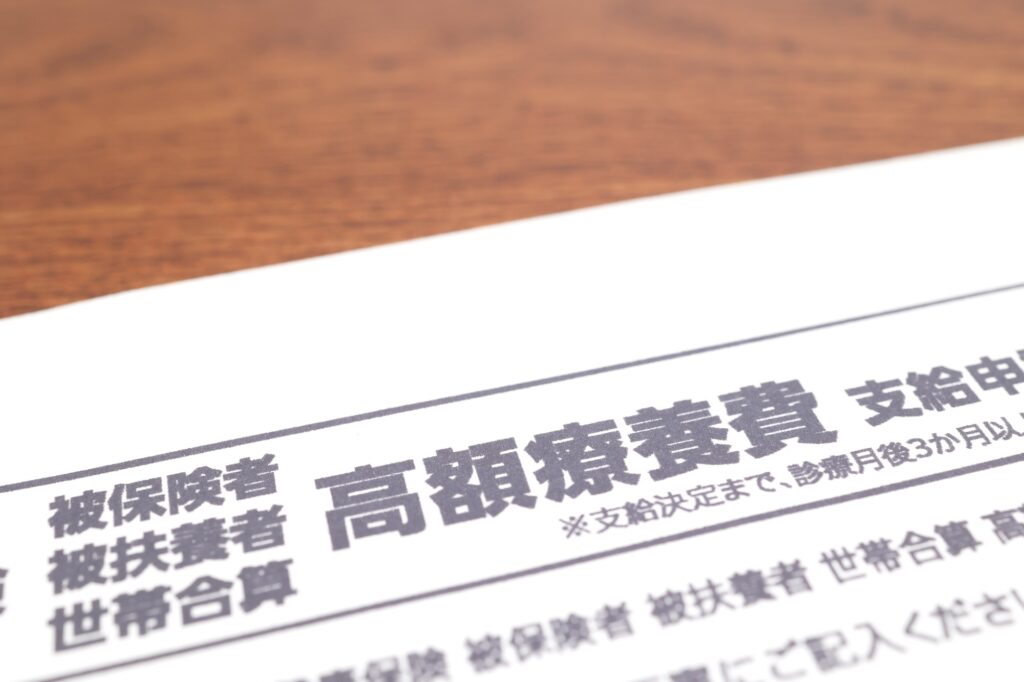
ひと月あたりの医療費が自己負担の上限額を超えることがあらかじめわかっている場合は、限度額適用認定証を取得しておくと良いでしょう。
限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、支払額が自己負担の上限額となり、一時的に医療費全額を負担せずに済みます。
限度額適用認定証は、加入する保険に申請することで取得できます。事前に申請手続きを済ませておきましょう。
※この記事は2022年11月時点の情報に基づいて作成しています。
高額療養費がいくら以上から適用されるかは、被保険者の年齢や所得によって変わってきます。一時的に全額を負担せずに済む、限度額適用認定証の仕組みもあります。あらかじめ上限を確認して、必要に応じて保険組合に申請手続きをしておくと良いでしょう。
N-B-22-0259(221206)
おすすめ記事
キーワード
article
おすすめ記事
contact
保険のご相談・お問い合わせ、資料請求はこちら
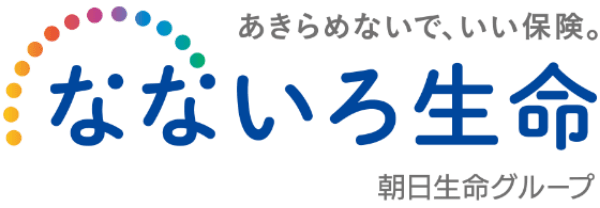
あきらめないで、いい保険。
『なないろ生命』は2021年4月に誕生した朝日生命グループの生命保険会社です。お客さまのニーズに応じて様々なプランをご用意しております。
電話でのお問い合わせ窓口
TVCMで見たなないろ生命の商品資料がほしい、保険加入の相談したいなどのお客様向け窓口